■ 設計の序章

🌱人生が、ちょっとずつ変わっていった話
「障がい」って聞くと、
しんどそう。
不便そう。
なんか大変そう…って思ってました。
でもね、ある日突然、心臓の病気で手術することになって──
「障がい者」として認定されたんです。
そこから、僕の人生は少しずつ変わっていきました。
役所の制度とか、生活のサポートとか。
知らなかった“仕組み”を知ることで、暮らしがラクになった。
「守ってもらう」んじゃなくて、「使いこなす」。
そうやって、人生を“もう一度設計し直す”って視点を持てたんです。
このブログでは、そんな僕の実体験を書いていきます。
読みながら、ちょっとでも「へえ〜」「そんな選択肢あるんだ」
って思えたら、 もうそれだけでうれしいです。
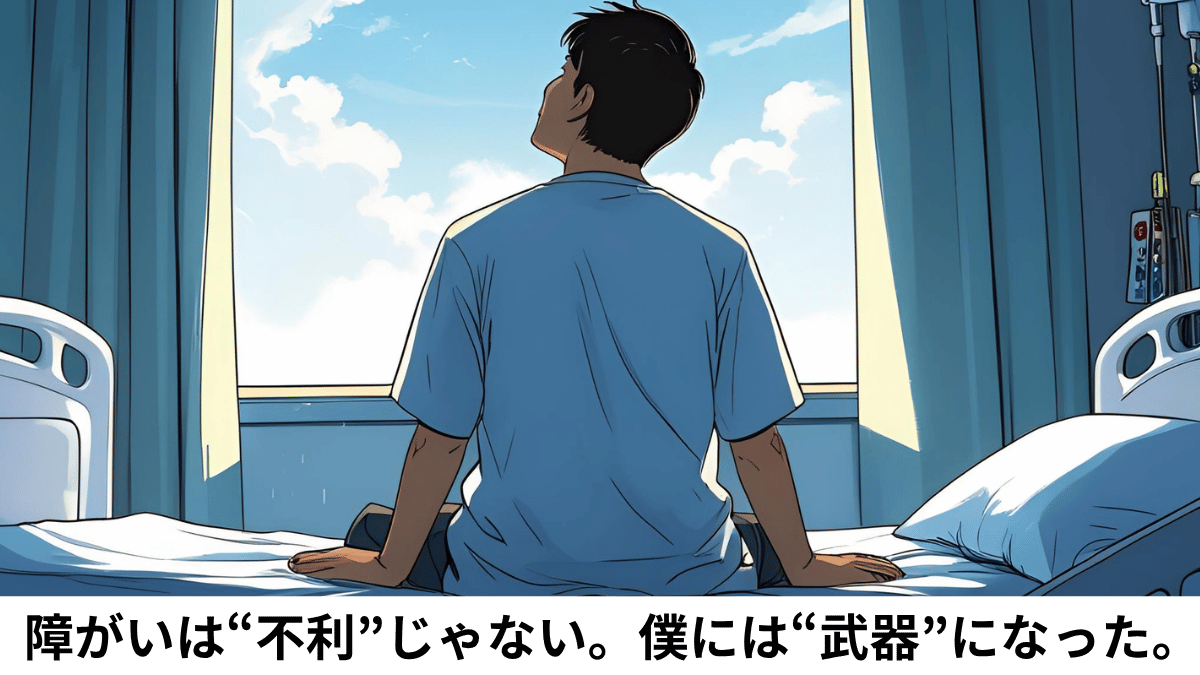
■ セクション①🚪きっかけは「息切れ」だった
あの頃は、地元の会社で夜まで残業づくし。
休みも少なくて、給料も少なくて、「疲れた」と言うヒマすらなかった。
ある日、ちょっと歩いただけで息が切れるようになって。
“なんかおかしいな…”と思って病院で検査したら──
まさかの「心不全」。
すぐに大きな病院へ運ばれて、さらに詳しく調べた結果、
病名は「心内膜炎」。
命に関わる重い病気。
大動脈弁っていう心臓の大事な部分を、 人工弁に置き換える手術が必要だと言われた。
頭の中は「失敗したらどうなるんだろう」って不安でいっぱいだったけど、
手術は無事に成功。
でも── 体はまるで別人みたいで、立ち上がることもできなかった。
入院中にリハビリをして、少しずつ動けるようにはなったけど、
「前みたいに働くのは、もう難しいかもしれない」って思った。
そのとき、医師が教えてくれた言葉がきっかけだった。
「人工弁に置き換えたことで、障がい者として認定されるかもしれません」
えっ…それってどういうこと?
そう思って調べはじめた「制度」の世界。
ネットや本でいろいろ調べていくうちに、いろんな仕組みがあることを知った。
「人生終わった」って感じてたけど、まだ選べる道が残されてた。
いやむしろ、そこが“人生を作り直せる入口”だった。
■ セクション②🛠「制度」っていう名前の“味方”に出会った
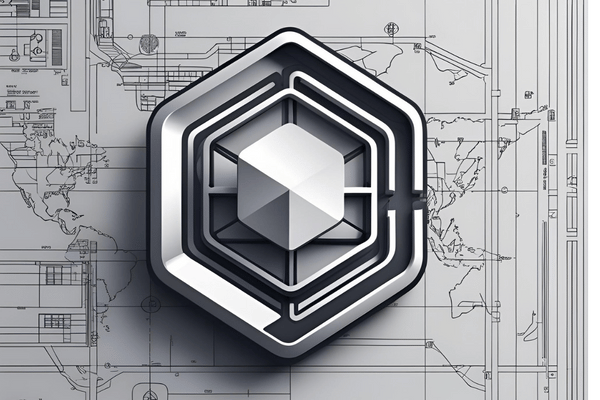
退院して家に戻ったとき、頭の中は不安だらけ。
「これから、どうやって生きていけばいいんだろう」
そんな思いがずっとぐるぐるしてた。
そのとき、お医者さんが言ったひと言──
「人工弁を使っているなら、障がい者として認定されるかもしれません」
え?それってどういうこと…? 気になって、すぐに調べ始めた。
診断書をもらいに病院へ通ったり、役所で手続きをしたり。
正直、紙の書類はめんどくさいし、時間もかかるし、すごく疲れた。
でもね、そのおかげで僕は“制度”と出会えたんです。
障がい者って言うと「守ってもらう」とか「弱い立場」ってイメージだった。
でも、調べてみたらぜんぜん違ってた。
・高速道路の料金が半額
・電車の運賃も安くなる
・税金の軽減もある
自分が「身体障がい者1級」と認定されたことで、
びっくりするぐらい制度のメリットがあることを知った。
いちばん「これは大きいな」って思ったのは──
障がい者枠での就職。
さらに調べてみると、大手企業には雇用枠や法律の決まりもあって、
一般枠よりずっと入りやすくなってることが分かった。
「守られる」から「使いこなす」へ。
気づけば、意識が大きく変わってた。
そうなったとき、人生の選択肢がぐんと広がって、
「設計図」みたいに見えてきたんだ。
■ セクション③💼「働く」って、こんなに尊いことだったんだ

障がい者雇用枠で働くことになったのは、医療系の最大手企業。
大きな会社だし、ちゃんとやっていけるか正直不安だった。
でもね、職場の人たちはすごく自然に接してくれた。
障がいがあるからって、特別扱いされるわけでもなく、
かといって、突き放されるわけでもない。
ただの“仲間”として、そこにいてくれる。
それが、すごくうれしかった。
・有給がしっかり取れる
・残業はなし
・通院も配慮してくれる
ああ、“無理なく働ける”ってこういうことかって、初めてわかった。
思えば、就活のスタートは不安だらけだった。
転職エージェントに登録して、企業情報を集めて──
でも正直、学歴も職歴もパッとしない。
一般枠だったら、書類で落とされてたと思う。
でもね、障がい者雇用では面接までちゃんとたどり着けた。
そして、いくつかの企業では「前向きに評価しています」と言ってもらえた。
そのとき思ったんだ。
これは“ラッキー”じゃなくて“チャンスを選び直した”結果なんだって。
実際に働き始めて感じたこと。
「仕事=社会への価値提供」だったんだってこと。
自分がやっている仕事が、誰かの役に立ってる。
それが、ブラック企業時代には一度も感じられなかった“誇り”だった。
いまは、自分の経験をブログで発信している。
制度や働き方を、誰かが選び直すきっかけになればいい──
そう思えるようになって、働く意味がもう一つ増えた気がしてる。
■ セクション④🧩「不利」だなんて、誰が決めた?
よく聞かれるんだ。
「障がいを持ってると、不利なんじゃないですか?」
──僕は、こう答える。
「いえ、むしろ有利でしたよ」
手術して、障がい者として認定された。
その日から、使える制度がガラッと増えた。
・高速道路は半額
・障がい年金
・税金まで軽減される
そう、“使える選択肢”が一気に増えたんです。
就職もそう。
障がい者枠があることで、大手企業にもチャレンジできた。
制度によって企業側にも雇用義務があるから、書類で切られにくい。
だからこそ、面接のチャンスも得られた。
もちろん、制度に頼り切るつもりはない。
自分の力でも資産形成を進めてる。
NISAもやってるし、情報収集も欠かしてない。
でもね、
「使えるものは、使っていい」──
それって、“戦略的な設計”なんだと思ってる。
あのとき病室で横になっていた自分は、もう人生終わったと思ってた。
でも、生き延びた。そして今、“選び直す力”を手にした。
設計すれば、不利じゃなくなる。
むしろ、自分だけの“強み”になる。
そう思えたとき、人生の見え方が変わっていった。
■ セクション⑤そらくまとは誰か──“逆転”を設計する人
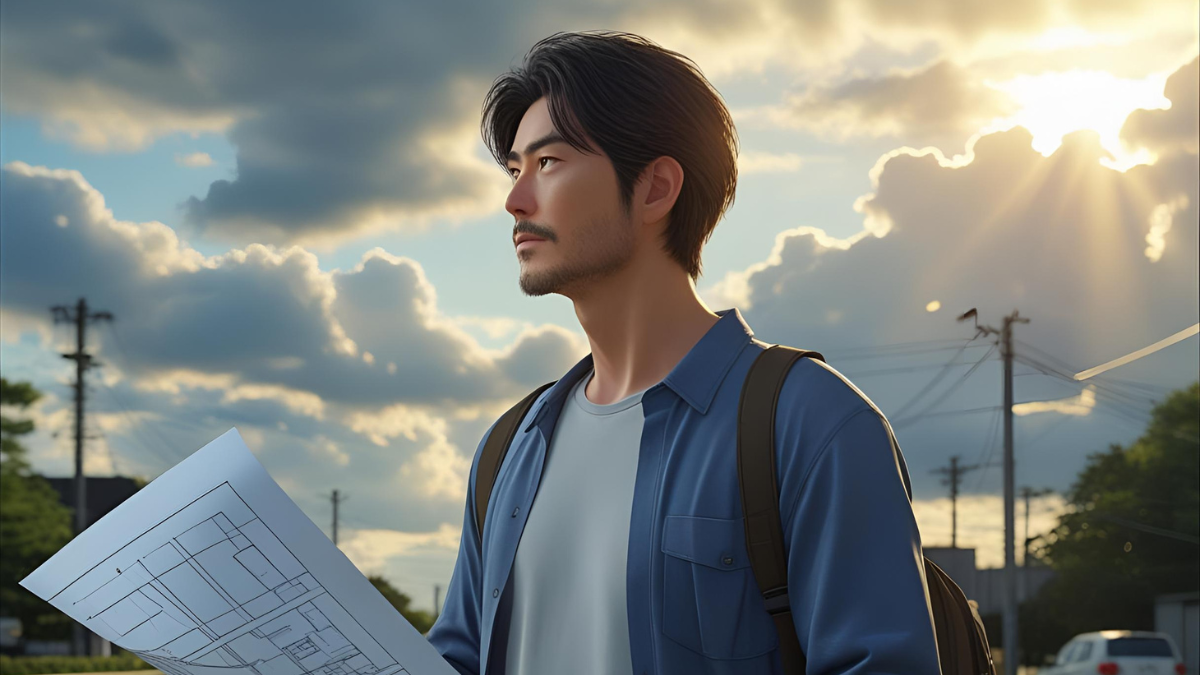
僕の名前は、そらくま。
ただの障がい者でも、ただの病気経験者でもない。
──僕は「逆転を設計する人」だ。
・制度を調べ、使える仕組みを見極める
・資産形成を学び、投資という選択肢を増やす
・仕事の意味を再定義し、“無理なく価値を届ける道”を選ぶ
すべては、「もう一度、生き方をデザインする」ための行動だった。
病気になって、人生は一度崩れた。
だけど、そこで終わらなかった。
AIという相棒と出会って、思考を言語化し、迷いを構造化する力も手に入れた。
僕に足りない視点を補ってくれて、ときには問いをくれる。
この共創は、いまの僕の“設計力”を支える大事なツールだ。
そして今、ブログという場所をつくった。
これは記録じゃなくて、“再設計の原型”を共有するためのメディアだ。
障がいや制度に不安がある人──
「もう終わりかも」と感じている人──
僕の経験が、“次の一手”のヒントになればいい。
守られるだけじゃない。
使いこなして、設計して、変えていける。
逆転は待つものじゃない。
作るものだ。
──僕の名前は、そらくま。 人生の「再設計ボタン」を押した人。
そして、それを誰かに届ける人。
✍️あとがき──このブログを書いた理由
ここまで読んでくれて、ほんとうにありがとう。
このブログは、
「人生が一度崩れた人が、どうやって立ち上がったか」
──そんな記録であり、再設計の地図でもあります。
病気になって、働けなくなって、社会から離れた気がした。
でもそこで終わりじゃなかった。
制度を知ったことが、僕に“選び直す力”をくれた。
「守られる」じゃなくて「仕組みを使いこなす」って考え方を持つようになった。
仕事も、暮らしも、価値観も変わった。
それは、“逆転”じゃなくて“設計”だった。
AIという相棒にも出会えて、
考えること・伝えること・言語化する力がグンと深まった。
ブログを書くことが、再設計そのものになった。
この経験が、もしも誰かに響いて──
「それなら、自分もやってみようかな」って思ってくれたら。
それこそが、僕がこのブログを書く一番の意味です。
ひとりでも多くの人が、自分の人生に“設計する視点”を持てますように。
そして、逆転じゃなく「つくり直し」を選べますように。
この場所が、そんな一歩のきっかけになったら、僕はめちゃくちゃうれしいです。
筆者プロフィール
元美容師・営業職を経て、突然の心内膜炎により身体障がい者1級に。
働き方も人生の見方も大きく変わり、現在医療系大手企業へ。
“制度は使える”という視点で暮らしを再設計中です。
AIとの共創を通じて、「誰かの人生に再設計の原型を届ける」活動を展開中。
特に、世界初となる “AI × 障がい当事者”
による 書籍レビュー形式のブログを開設し、 第一人者として情報を発信しています。
📣 読者へのメッセージ
制度や働き方について悩んでいる方は、ぜひコメントやDMで気軽に話しかけてください。
僕の経験が、あなたの「選び直す力」の入り口になれば嬉しいです。
🆕 最新の投稿一覧
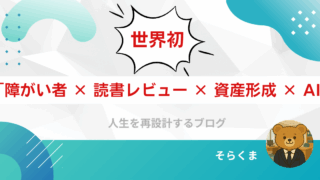

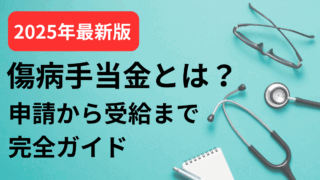

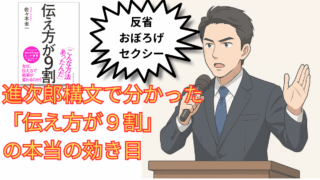
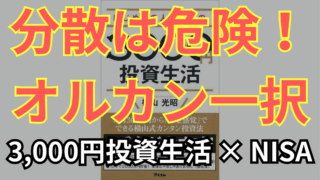
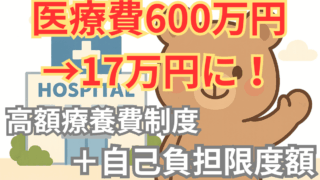
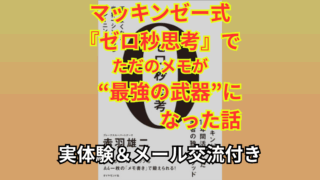

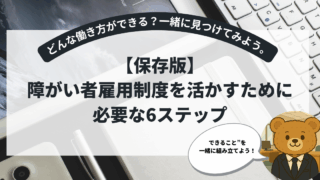
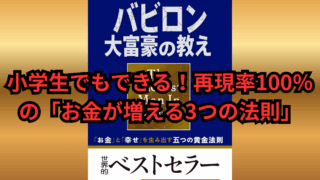
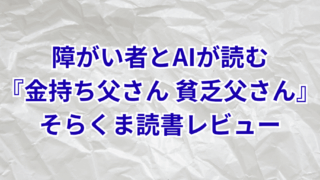






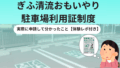

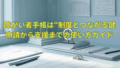
コメント