🌱 はじめに:どうしてお金は貯まらないの?
「お金を貯めたいな」と思っても、なかなかうまくいかないことってありますよね。
たとえば──
- セールで「安い!」と思って買ったのに、あまり使わなかった
- サブスクを解約し忘れて、気づいたら何か月もお金を払っていた
- 「今月こそ貯金しよう」と思ったのに、最後にはお金が残らなかった
こんなことがあると「自分はダメだな」「意思が弱いからだ」と思ってしまうかもしれません。
でも本当はちがうんです。
人間はみんな、お金の見せ方にだまされやすいクセをもっているんです。
このクセを研究したのが「行動経済学」という学問です。
名前はむずかしそうですが、実はとても身近なもの。
スーパーのチラシやネットの広告、アプリの料金プラン──毎日の生活の中にこの仕組みはいっぱい使われています。
もともと行動経済学は「どうすればもっと買ってもらえるか」を考えるために発展しました。
でも、もしその仕組みを私たちが知っていたら?
それは無駄遣いを止めるための道具になります。
この記事では、本『サクッと分かるビジネス教養 行動経済学』を参考にして、
とくに節約に役立つ「3つの心理のクセ」をわかりやすく紹介します。
読み終えたときには、きっとあなたも「だまされる人」から「お金を守れる人」に変われるはずです。
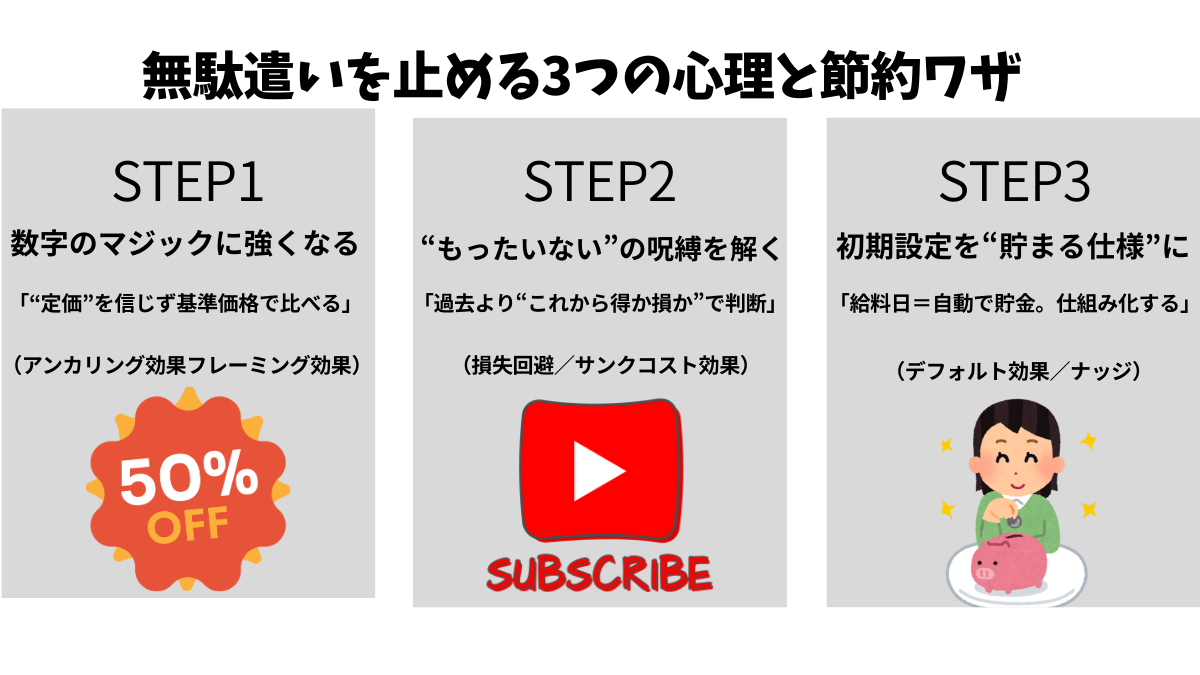
🟦 STEP1|アンカリング効果を節約に使う
― 「最初の数字」にだまされない
🧠 アンカリング効果とは?
行動経済学では、人は「最初に見た数字」を基準にしてしまうクセがあると説明されています。
たとえば、洋服の札にこう書いてあったらどう感じますか?
👕 「定価10,000円 → 本日限定6,800円!」
思わず「3,200円も安い!お得!」と思ってしまいますよね。
でも、もしその服のふだんの相場が6,500円くらいなら…?
実はまったくお得じゃなく、ほとんど“いつもの値段”なんです。
これが アンカリング効果=最初の数字に引っぱられるクセ です。
💸 このクセが生む無駄遣い
- 「◯円引き!」につられて、本当は安くない物を買ってしまう
- 「定価」と比べて“得した気分”になり、不要なものまで買ってしまう
✅ 節約に活かすには?
アンカリング効果を逆に使って、自分の基準価格をアンカーにするのです。
- よく買うものを3つだけ(米・牛乳・卵など)決めて、ふだんの値段をメモ
- 服や家電なら、ネットや比較サイトで「相場価格」をチェックしておく
👉 店が見せる「定価」ではなく、自分の基準価格と比べるのがポイント。
🧩 具体例
- スーパーで「定価300円 → 200円!」のお菓子
- 基準価格メモを確認すると「いつも200円前後」
- → 実はお得じゃないから買わない!
✨ まとめ
「定価から◯円引き」にだまされるのは、アンカリング効果という人のクセ。
でも、その仕組みを知れば逆に利用できます。
“自分の基準価格”をアンカーにすれば、ムダな買い物はぐっと減るのです。
🔍 ちなみに…
数字にだまされるクセはこれだけではありません。
同じお金でも「月500円」と言われると安く感じ、「年6,000円」と言われると高く感じる。
こうした 言い方で感じ方が変わるクセ を、行動経済学では フレーミング効果 と呼びます。

👇
🟦 STEP2|サンクコスト効果で“もったいない地獄”から抜ける
― 「せっかく払ったのに」で続けない
🧠 サンクコスト効果とは?
行動経済学には「サンクコスト効果」というクセがあります。
すでに払ったお金や時間はもう戻ってこないのに、
「もったいないから」とやめられない心理のことです。
- 例:見ていないサブスクを解約できない
- 例:ぜんぜん行かないジムに会費を払い続ける
👉 「過去の支出」にしばられて、未来のお金まで失うのがサンクコスト効果です。
💸 このクセが生む無駄遣い
- サブスク:無料体験をそのまま放置 → 月980円が毎月消える
- ジム:行かないのに「せっかく契約した」と払い続ける
- ポイント:失効がイヤで、必要ない物に交換してしまう
✅ 節約に活かすには?
サンクコスト効果を逆に使って、やめるきっかけを作ります。
- 最初に“やめる日”を決める
契約したその日に、更新前日をスマホにアラーム登録。 - 回数で判断する
「週1回以上使わなかったら解約」とルールを決める。 - 浮いた分を見える形で貯金する
本来払うはずだった980円を別口座に移す。
👉 「続ける理由」ではなく「やめる基準」を先に作るのがポイント。
🧩 具体例
- 動画サブスク:月980円
- 先月は1回しか見なかった → 1回=980円は高い
- 解約 → 980円をそのまま貯金アプリへ
- → 「もったいない出費」が「守れたお金」に変わる
✨ まとめ
サンクコスト効果は「過去に払ったからやめられない」クセ。
でも知っていれば逆に利用できます。
“やめる日を決める・回数で判断・浮いた分を貯金”
これだけで、固定費のムダはぐっと減ります。
🔍 ちなみに…
人は「もったいない」だけじゃなく、損をする痛みをものすごく大きく感じるクセもあります。
1000円得する喜びより、1000円失うショックの方がずっと大きいのです。
これを 損失回避バイアス と呼びます。

🟦 STEP3|デフォルト効果で“自動的に貯まる仕組み”をつくる
― 初期設定を味方にする
🧠 デフォルト効果とは?
人は「最初に用意された選択肢」を、そのまま選んでしまうクセがあります。
これを デフォルト効果 と呼びます。
- 例:会社の福利厚生で「自動加入」が初期設定になっている保険 → 多くの人がそのまま加入
- 例:スマホの通知や契約プラン → 面倒なので初期設定のまま使う
👉 人は「わざわざ変える」のが面倒で、デフォルトを受け入れてしまうのです。
💸 このクセが生む無駄
- 給与口座に入ったお金 → 使ってから貯金しようと思うと、なかなか残らない
- 携帯やネット回線のプラン → 初期設定のまま払い続けて割高に
- サービスの自動更新 → 解約せずにお金が流れ続ける
✅ 節約に活かすには?
逆に言えば、最初の設定を“節約寄り”に変えてしまえば、自動でお金が貯まるということ。
- 貯金をデフォルトにする
給料日には自動振込で「先取り貯金口座」へ。
→ 何もしなくても貯金がたまる。 - 解約をデフォルトにする
サブスクは「自動更新なし」に設定。
→ 使わないならそのまま終了、必要な月だけ入り直せばいい。 - 安いプランをデフォルトにする
スマホや電気は「最安プラン」を基本に。
→ 変更するときに「本当に必要?」と一度考えるきっかけになる。
🧩 具体例
- 給料日:自動で1万円が貯金口座へ移動
- もし手をつけなければ1年で12万円たまる
- → 「努力せずに貯まっている」状態を作れる
✨ まとめ
人は「初期設定のまま」に従いやすい。
だからこそ、初期設定を“お金が貯まる方”に変えることが節約の近道。
努力しなくても、自動でお金が守れるようになるのです。
🔍 ちなみに…
この「デフォルト効果」は、行動経済学でいう ナッジ(nudge) の代表例でもあります。
ナッジとは「自由は残しつつ、よりよい選択をそっと後押しする工夫」のこと。
初期設定を味方にすれば、自然とお金を守れる方向に自分を“ナッジ”できるのです。

🌱 まとめ|クセを知れば、お金は自然と守れる
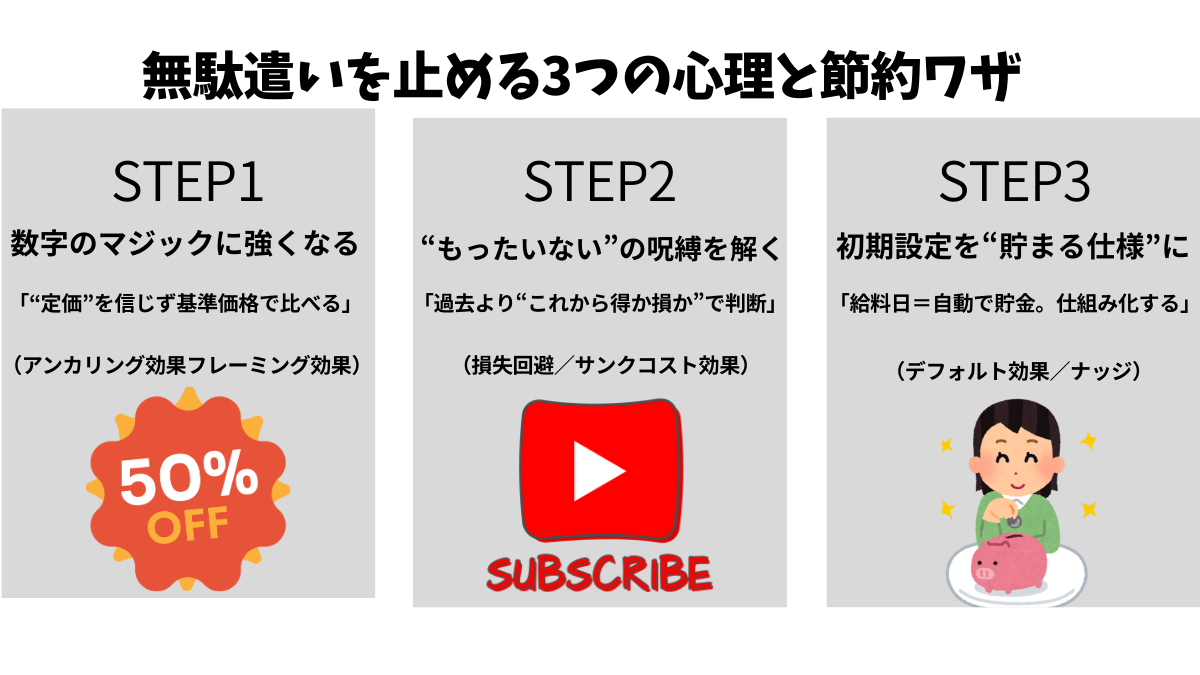
行動経済学には、人がお金を使うときにハマりやすいクセがたくさんあります。
今回見てきたのはその中でも、特に生活に直結する3つでした。
- アンカリング効果
最初に見た数字にだまされない。自分の基準価格を持つ。 - サンクコスト効果
「せっかく払ったのに」で続けない。やめる基準を最初に決める。 - デフォルト効果
初期設定を味方にする。自動でお金が貯まる仕組みに変える。
お金の知識って、「投資」や「資産形成」のようにむずかしい話になりがちです。
でも実は、日々の買い物やサービスの契約をちょっと見直すだけで、ムダづかいはぐっと減らせるんです。
つまり節約は、「努力や我慢」よりも「人のクセをうまく利用する」ことが近道。
行動経済学を知っていれば、そのクセに気づき、逆に活かすことができます。
💡 最後に合言葉をもう一度。
- 定価より、自分の基準価格で比べる
- “やめる日”を最初に決めておく
- 貯金を初期設定にしておく
🙌 あなたも今日から始めてみよう
行動経済学はむずかしい学問のように見えますが、実は日常のお金の使い方をラクに変えるヒントです。
- 「数字にだまされない」
- 「もったいない地獄から抜ける」
- 「初期設定を味方にする」
どれも、特別な知識や努力はいりません。
ちょっと視点を変えるだけで、お金の流れは自然とよくなります。
💡 今日からできることはシンプルです。
- スーパーに行ったら「自分の基準価格」で比べてみる
- サブスクに入るときは「やめる日」をすぐカレンダーに入れる
- 給料日に「先取り貯金」を自動で振り分ける
こうした小さな工夫が、1か月、1年と積み重なって、未来の安心をつくります。
👉 ぜひ今日から、ひとつだけでも試してみてください。
あなたの「節約習慣」が、ここから始まります。
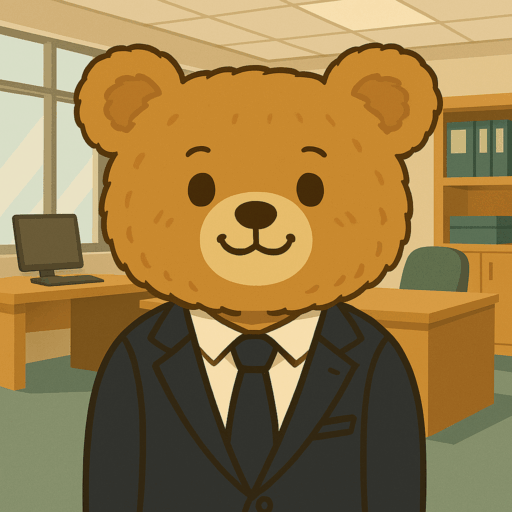
人生逆転中の著者、そらくまです。
もともとは美容師や営業職をしていましたが、突然の心内膜炎で身体障がい者1級に。
そこから働き方も人生の見方も大きく変わり、今は医療系の大手企業で働いています。
「制度は使える」という視点を軸に、暮らしをもう一度デザインし直すことに挑戦中です。
さらにAIと共に学び・発信することで、
**「誰かの人生を再設計するヒントを届けたい」**と活動しています。
特に、世界初の試みとして──
「障がい者 × 読書レビュー × 資産形成 × AI」
この4つを掛け合わせたブログを立ち上げ、第一人者として情報を発信しています。
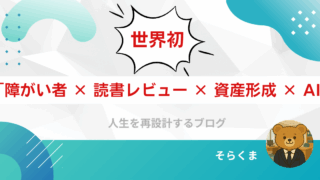

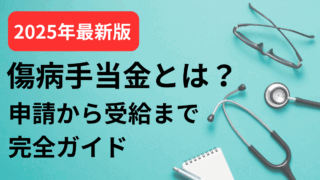

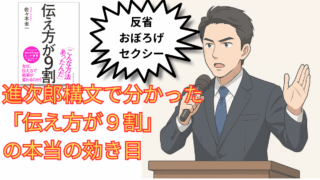
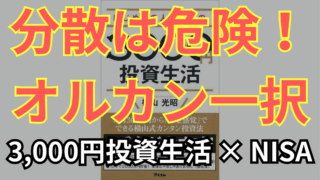
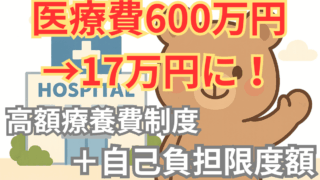
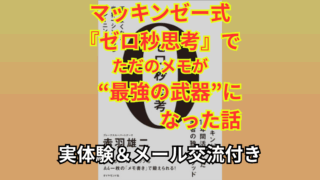

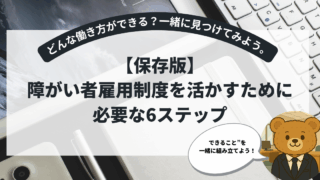
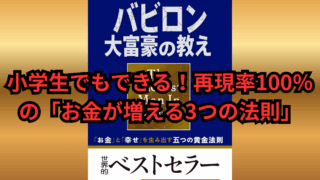
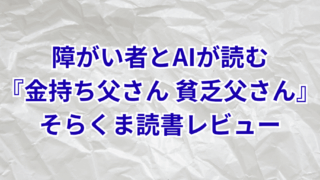



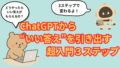
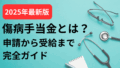
コメント