- ✍️ 第1章:障がい者雇用のしくみと現実
- 🌱 はじめに
- 🧠 制度は「暮らしをつくるツール」
- ✅ 障がい者雇用の基本ルール
- 🧭 制度の入口で知っておきたいこと
- 🤝 企業とのギャップ
- 💡 就職までの流れ
- ❓ よくある不安と答え
- 📌 まとめ
- ✍️ 第2章:制度の使い方と合理的配慮
- 🌱 はじめに|“伝える”は「説明」ではなく「設計」
- 🧠 僕が工夫した伝え方
- ✅ 合理的配慮とは「お願い」ではなく「共同設計」
- 📊 企業にとってのメリット・デメリット
- 📝 診断書は「医療記録」ではなく「生活の設計図」
- 🤝 前例がない職場での経験
- 💬 まとめ|“伝える”は、あなた自身の設計力
- ✍️ 第3章:制度と働き方のそらくま設計
- 🌱 はじめに|“働き方が変わる”という制度の底力
- ✅ 制度が守ってくれたこと・開いてくれたこと
- 🤝 AIとの協働で広がった「情報設計」
- 🗺️ 暮らしを再構築する“編集者”としての働き方
- 💬 まとめ|制度は「働ける形」を組み立てる素材箱
- ✍️ 第4章:「制度を使える人」になるための設計図
- 🌱 はじめに|制度は「読むもの」ではなく「動かすもの」
- 🛠️ 「制度を使える人」になる6ステップ
- 🔍 読者タイプ別アプローチ|制度の使い方は人それぞれ
- 💬 まとめ|制度を“使う人”になろう
- 🔜 次回予告|実践編に進みます
✍️ 第1章:障がい者雇用のしくみと現実
🌱 はじめに
「就職、どうすればいいんだろう?」──そんな不安、ありますよね。
制度を知ることはもちろん大事ですが、実はそれだけでは十分ではありません。
本当に大切なのは、
👉 「どう働いて、どう暮らすか」を自分で考えていくこと。
制度は、そのための“道具”なんです。
🧠 制度は「暮らしをつくるツール」
[配慮してもらうだけ] → 受け身の姿勢
[どう働きたいか考える] → 暮らしを自分で設計する姿勢
僕自身、制度を使って働き始めたときに感じたのは、
「守ってもらう仕組み」ではなく「自分らしい暮らしをつくるための仕組み」 なんだ、ということでした。
✅ 障がい者雇用の基本ルール
📊 法律とルール
この制度は 「障がい者雇用促進法」 という法律に基づいています。
法律:障がい者雇用促進法
↓
企業は、従業員の中に一定割合の障がい者を雇うことが義務
- 法定雇用率(2024年現在)
民間企業:2.5%
国や自治体:2.6〜2.9%
👉 たとえば100人規模の会社なら、2〜3人は必ず障がい者を雇う必要があるんです。
🎫 対象となる人
この制度を使えるのは、障がい者手帳を持っている方です。
- 身体障がい者手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 療育手帳
就職活動では 「障がい者雇用枠」 から応募することになり、
面接や選考の流れが一般枠と違う場合があります。
🧭 制度の入口で知っておきたいこと
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 法定雇用率 | 民間企業は2.5%。未達成の企業は行政指導や納付金制度の対象に。 |
| 雇用枠 | 手帳を持っている人が対象。履歴書に記載することが多い。 |
| 求人探し | ハローワークの専門窓口/支援事業所/就労移行支援などを活用。 |
🤝 企業とのギャップ
表向きは「制度を活用しています」と宣伝していても、
現場ではこんな声が聞こえてきます。
「どんな仕事をお願いすればいいのかわからない…」
僕が出会った企業の中には、
「配慮=とにかく軽い仕事」
と考えてしまうところもありました。
でも、本当に必要なのは──
👉 「その人ができること」と「企業の役割」を一緒に考える対話 です。
💡 就職までの流れ
[手帳を取得]
↓
[相談・求人探し]
↓
[応募・面接]
↓
[採用・契約]
↓
[働き始める]
- 障がい者手帳の取得(診断書・等級が必要)
- ハローワークなどで職業相談・求人探し
- 応募・面接(必要な配慮を相談)
- 採用通知と雇用契約
- 実際に働き始める(配慮やフォローを受けながら)
❓ よくある不安と答え
面接でどこまで話す?
👉 すべて話す必要はありません。
「働くために必要なこと」だけ を伝えれば大丈夫。
- 例:「人混みが苦手なので、静かな部屋で面接できると助かります」
- 例:「視覚過敏があるので、資料は白黒でお願いします」
給与や契約は同じ?
基本は一般雇用と同じですが、会社ごとに違いがあります。
- 例:「契約社員だけど、半年後に正社員登用のチャンスがある」
- 例:「勤務時間が短いので、時給契約」
👉 面接で「契約内容」「昇給」「更新基準」を確認しておくと安心です。
周囲に障がいを伝えるべき?
無理に伝える必要はありません。
自分が働きやすいかどうか で決めましょう。
- 例:「上司にだけ伝える」
- 例:「自分で工夫して、周りには伝えない」
体調が不安定になったら?
相談できる先をあらかじめ確認しておくと安心です。
- 人事担当
- 上司
- 産業医
- 外部の支援窓口
👉 「困ったときに声を出せる仕組み」があるだけで、不安は大きく減ります。
📌 まとめ
障がい者雇用制度は、ただ「守られるための制度」ではありません。
制度 = 暮らしを自分で設計するためのツール
不安や迷いを抱えることも、すでに「設計の第一歩」。
そこから、自分らしい働き方を少しずつ形にしていきましょう。
✍️ 第2章:制度の使い方と合理的配慮
🌱 はじめに|“伝える”は「説明」ではなく「設計」
障がい者雇用の面接では、
「何ができて、何ができないか」をどう伝えるか──ここが最初の壁です。
でも、伝え方を間違えると…
- 「この人は自分の障がいを理解していない?」
- 「軽作業しか任せられないかも…」
そんな誤解を与えてしまうことがあります。
僕自身、最初は「特に制限はありません」と伝えてしまい、面接官を戸惑わせたことがありました。
🧠 僕が工夫した伝え方
ただ「制限はない」と言うのではなく、
👉 健康管理の工夫を背景にした伝え方 に変えました。
例:
「僕は体調を維持するために毎日ウォーキングをしています。
そのため、過度な残業を控えていただけると助かります。」
📌 この一言で伝わること
- 障がいを前向きに捉えている
- 自己管理に取り組んでいる
- 暮らし目線で「できる・できない」を整理できている
- 企業にとって「設計できる人材」である
✅ 合理的配慮とは「お願い」ではなく「共同設計」
企業には「合理的配慮」をする義務があります。
でも実際には、“お願いごと”ではなく、一緒に働き方をつくる協働プロセスなんです。
合理的配慮の例
- 業務の調整(激しい運動 → デスクワーク)
- 残業の抑制(生活リズムを守る)
- 通院の配慮(有給や日程調整)
- コミュニケーション支援(メモ・視覚的情報・こまめなフィードバック)
📊 企業にとってのメリット・デメリット
| 視点 | 内容 |
|---|---|
| メリット | ・法定雇用率を達成できる ・社会的責任の実現 ・多様性で職場が成熟 ・業務再設計で効率が上がることも |
| デメリット | ・業務内容の調整が必要 ・体調変化への対応力が求められる ・社内の理解を広げる必要 ・初期のサポートコスト |
👉 これを「負担」と見るのではなく、支え合いに変えていく力が「共同設計」にはあります。
📝 診断書は「医療記録」ではなく「生活の設計図」
面接官は医師ではありません。
だから、病名や等級だけを伝えても理解は深まりません。
大切なのは 👉 暮らしの中でどう困っているか・どう工夫しているか を伝えること。
文章が難しければ、履歴書や別紙を使うのもありです。
記載内容の例
- 障がいの経緯や時期
- 医師の指導内容(運動・業務制限など)
- 日常の工夫(ウォーキング・体調管理など)
- 働く上での希望(勤務時間・業務範囲など)
📌 これがあると、企業との「すり合わせ」がとてもスムーズになります。
🤝 前例がない職場での経験
僕が就職したとき、会社として障がい者の採用経験はあっても、
配属先の部署では前例がありませんでした。
だから面接では配慮に関する質問が次々と飛んできました。
- 「何を任せればいいのか分からない」
- 「どんな環境整備が必要なのか想像できない」
このときに役立ったのが「お願い」ではなく 働き方の設計図。
それを丁寧に言葉にすることで、僕は「一緒に設計できる人」として見てもらえました。
💬 まとめ|“伝える”は、あなた自身の設計力
合理的配慮は「もらう」ものではなく、
👉 自分の働き方を組み立てる権利(編集権) です。
- 生活リズムや体調の特徴を言葉にする
- 得意・不得意を業務に当てはめて整理する
- 伝えることそのものを、設計の第一歩にする
✨ あなた自身が「設計者」として歩み出すこと。
それが、この章での一番のメッセージです。
✍️ 第3章:制度と働き方のそらくま設計
🌱 はじめに|“働き方が変わる”という制度の底力
障がい者雇用制度は、就職の「枠」にとどまらず、
👉 人生の時間・働き方・暮らし方 にまで影響してきます。
僕自身も、制度を使う前はブラック企業で、
「寝るためだけに帰る毎日」を過ごしていました。
働くことが、生きることのすべてになりかけていたんです。
でも今は──
- ブログを書く時間がある
- 本を読む時間がある
- 睡眠リズムが整い、体調が安定している
🧩 働き方を設計するとは、 「暮らしの余白を取り戻すこと」 でもあるのだと思います。
✅ 制度が守ってくれたこと・開いてくれたこと
具体的に感じた“ありがたさ”
- 残業:多少OKと伝えていたが、実際は完全ゼロ残業で設計してもらえた
- 通院:普通なら「入社6か月後から」の有給が、初日から使えた
これは制度の力か、会社の文化かは分かりません。
でも確実に言えるのは…
🛠️ 「障がいを抱えながら働く」という視点が、働き方を再編集する力になっていた ということです。
🤝 AIとの協働で広がった「情報設計」
初めて制度を使って働くとき、僕自身も制度に詳しいわけではありませんでした。
だからこそ、転職エージェントに提出する書類を AIと一緒に設計 しました。
AIに助けてもらったこと
- 制度の意味を整理して言葉にする
- 制限や希望の伝え方を分かりやすくする
- 志望動機や配慮事項の表現を客観的に確認する
✨ その結果、
「制度に守られる自分」から「制度を使いこなす自分」へと変わっていけたんです。
👉 AIは、まさに “働き方を設計する補助線” でした。
🗺️ 暮らしを再構築する“編集者”としての働き方
昔の僕は「働きすぎで暮らしが見えない生活」でした。
でも今は、制度を使って働き方を組み直したことで──
- 余白があるから 本が読める
- 睡眠が安定しているから 集中できる
- 書く時間があるから 自分の働き方を振り返れる
これらはすべて、制度によって編集された新しい働き方の成果です。
そして僕自身が「制度を活かして働き方をデザインできる人」になった。
それが そらくま設計 という生き方の芯になりました。
💬 まとめ|制度は「働ける形」を組み立てる素材箱
障がい者雇用制度は、就職の窓口であると同時に、
👉 自分らしく働く条件を組み立てる素材箱 です。
組み合わせられる素材の例
- 時間の設計(残業や休息のバランス)
- 通院や生活リズムの調整
- 伝える力の工夫
- 情報との付き合い方の再設計
制度を活用できたとき、
「働くこと」そのものが生き方を再構築するプロセス に変わっていきます。
📘 次章では、制度を“使える人”になるために──
情報整理のコツ、申請ステップ、読者タイプ別のアプローチを一緒に見ていきましょう。
✍️ 第4章:「制度を使える人」になるための設計図
🌱 はじめに|制度は「読むもの」ではなく「動かすもの」
障がい者雇用制度を「よし、使おう!」と思ったとき、
最初にぶつかるのは 👉 準備の大変さ かもしれません。
🧾 ハローワークで申請するときは、多くの書類を自分で揃える必要があります。
とくに障がい者雇用の場合は、提出書類が通常より多くなることもしばしば。
だからこそ、僕は 転職エージェントの活用 をおすすめします。
制度に詳しい担当者が、書類づくりから面接対応まで支えてくれる──
それだけで精神的な負担がぐっと軽くなりました。
この章では「知っている」で終わらせず、
🌱 「暮らしの中で制度を活かす力」 をつけるためのステップを整理していきます。
🛠️ 「制度を使える人」になる6ステップ
① 制度を理解する
↓
② 自分の状況を整理する
↓
③ 相談先を見つける
↓
④ 伝え方を設計する
↓
⑤ 書類・志望動機を準備する
↓
⑥ 働きながら調整する
ステップごとの内容
- 制度を理解する
法定雇用率、手帳の種類、企業の義務を把握する - 自分の状況を整理
診断書、通院頻度、体調の波を言葉にする - 相談先を見つける
ハローワーク、就労支援、エージェントなどを検討 - 伝え方を設計
手帳の開示方法、面接での説明、配慮の伝え方 - 書類と志望動機を設計
前向きな気持ちを反映させた履歴書・志望動機を用意 - 働きながら調整
有給・通院・相談体制などを定期的に見直す
👉 この流れを一歩ずつ踏むことで、制度は「ただのルール」から
🧭 「自分で選択できる道具」 へと変わります。
🔍 読者タイプ別アプローチ|制度の使い方は人それぞれ
あなたはどのタイプに近いですか?
3タイプが混ざっていてもOK。
「いちばん引っかかる部分」から始めるのがおすすめです。
🔹 情報整理タイプ|道順さえ分かれば進める
→ 書類一覧・提出スケジュール・面接までのフローを見える化
🔹 不安タイプ|伝え方に自信がない
→ 履歴書テンプレ・面接での言い方例・安心できる相談フレーズを用意
🔹 想像力タイプ|図解や体験談で理解したい
→ 「制度活用フロー図」+「制度で変わった暮らし」のストーリーを参考に
📖 大事なのは「制度を知る」ことではなく、
👉 「自分の言葉で制度と向き合える状態」をつくること です。
💬 まとめ|制度を“使う人”になろう
🌱 社会はあなたを必要としています。
障がい者雇用は「不利」ではなく、むしろ 安心して働ける道 を開くものです。
制度は、あなたの人生を変える 設計道具。
読むだけでなく、実際に動かしてこそ力を発揮します。
✨ そらくま設計は、あなたが制度を使える人になるまで、これからも伴走していきます。
🔜 次回予告|実践編に進みます
次章では「面接での実体験」を中心にお届けします。
- 面接でよく聞かれる質問は?
- 履歴書にはどこまで書けばいい?
- 注意しておくべきポイントは?
「面接ってこわい…」と感じる人にも安心して準備できるよう、
僕の経験をベースに 実践的なヒント をまとめていきます。
元美容師・営業職を経て、突然の心内膜炎により身体障がい者1級に。 働き方も人生の見方も大きく変わり、現在医療系大手企業へ。 “制度は使える”という視点で暮らしを再設計中です。
AIとの共創を通じて、 「誰かの人生に再設計の原型を届ける」活動を展開中。
特に、世界初|「障がい者 × 読書レビュー × 資産形成 × AI」 人生を再設計するブログを開設し、 第一人者として情報を発信しています。
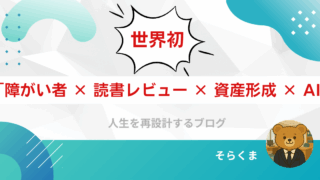

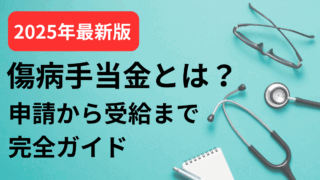

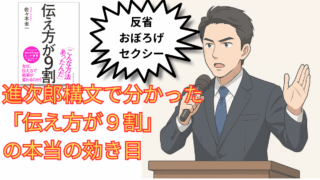
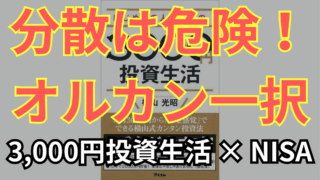
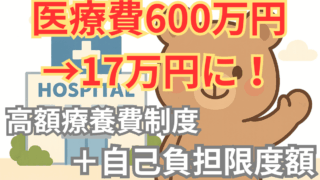
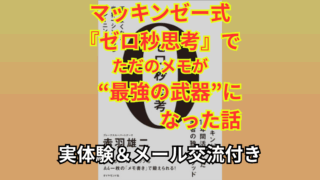

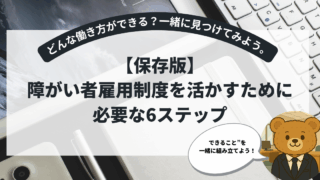
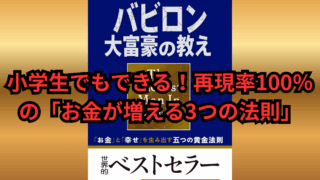
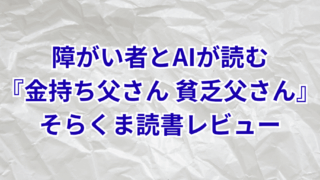


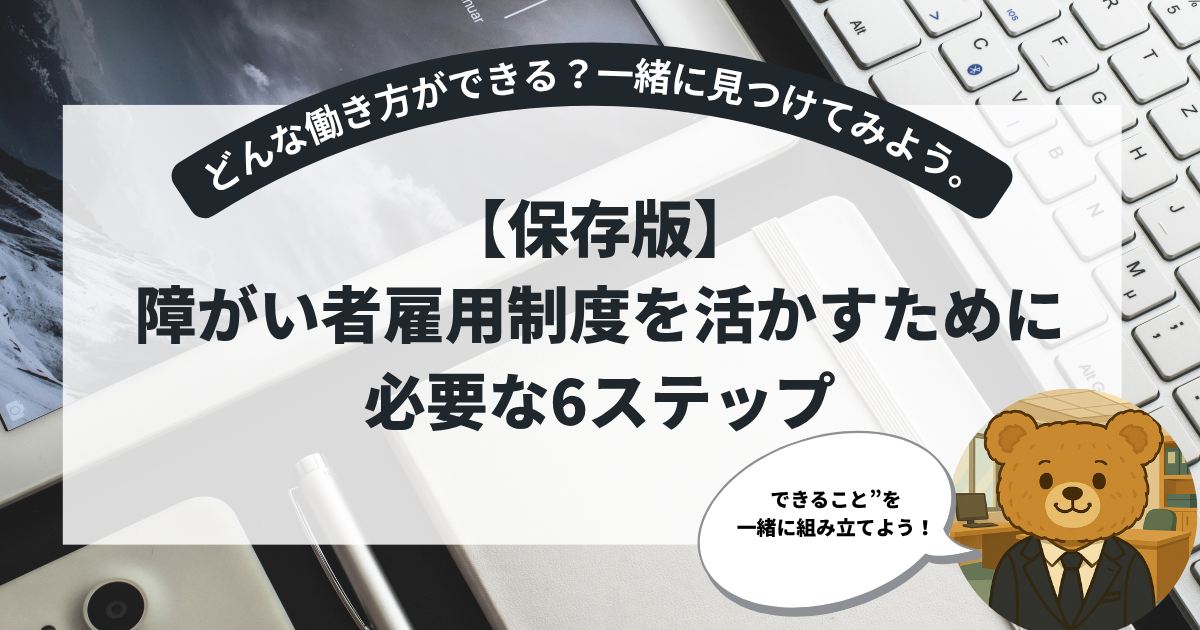
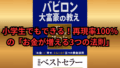

コメント